\ 1日1回のポチッ!が嬉しいです /
子どもが生まれた!出産関係手続きの解説【新米パパ向け】
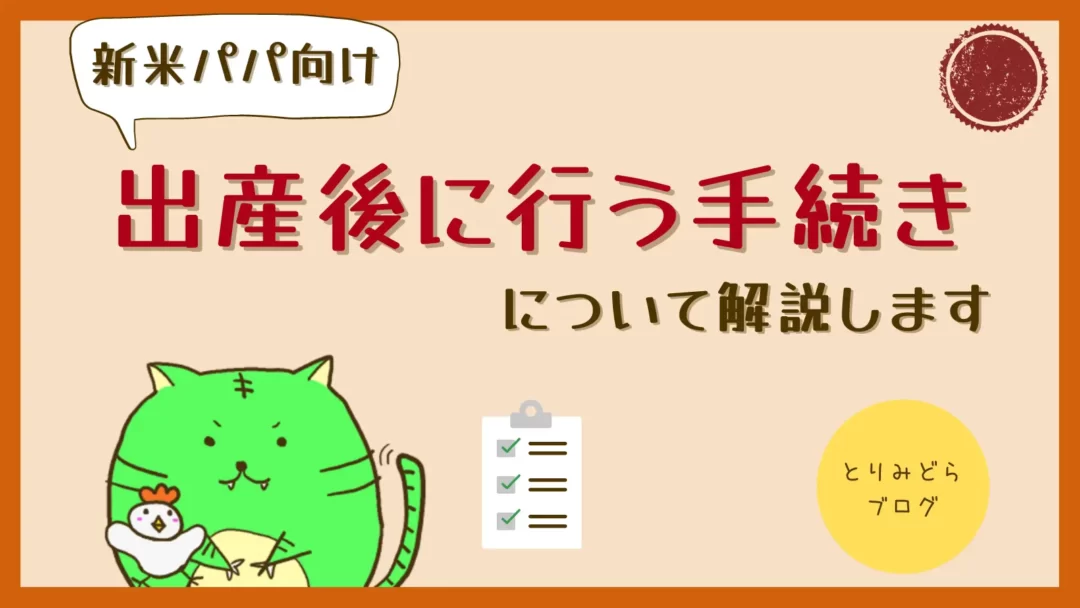
 とりみどら
とりみどらこんにちは!とりみどら(@torimidora)です!
新米パパのみなさん!これからパパになるプレパパのみなさん!そして、もうパパだけどパートナーが現在妊娠中の方!
この記事では、赤ちゃんが生まれたときに必要な手続きの解説と、経験して得られた「これは知っておいた方がいい!」と思ったことを共有しますので、ぜひ読んでいってください。
本題の前に簡単に自己紹介を。
 とりみどら
とりみどらとりみどらと申します。
5歳と2歳の娘を持つアラサーの父です。
何気ない日常をどうしたら幸せにできるのか考えて実践してみるのが好きです。
「自分の好きと楽しいを共有する」ことをモットーとして、主に趣味や好きな物に関する情報を紹介しています。
2児の父として子育て情報も発信していきますので、よろしくお願いします!
- 手続きは早めにしよう!
- 役所は出生届さえ出せば、あとは言われたとおりでOK
- 詳細は必ず自分の自治体・勤め先で確認しよう!
- 手続きは新米パパの第一頑張りポイント!ママの信頼を勝ち取ろう!
はじめに
まずは、
 とりみどら
とりみどらご妊娠、ご出産、おめでとうございます!
赤ちゃんが生まれてホッと一息つきたいところですが、出産後には様々な手続きをする必要があります。
「なんか難しくてよくわかんないんだよね…」
という人(当時の自分)のために、できる限りわかりやすく解説しますのでご安心ください!
ここでは一般的なケースとして、
- 会社勤め
- パパの方がママより収入が高い
- 臨月に自然分娩で出産時に問題が起きていない
という条件に当てはまる方をメインに想定して記載しています。
また、住んでいる自治体や勤め先の会社によって、制度は様々です。
詳細については、必ずご自身の自治体や勤め先にご確認ください。
役所の手続
出生届
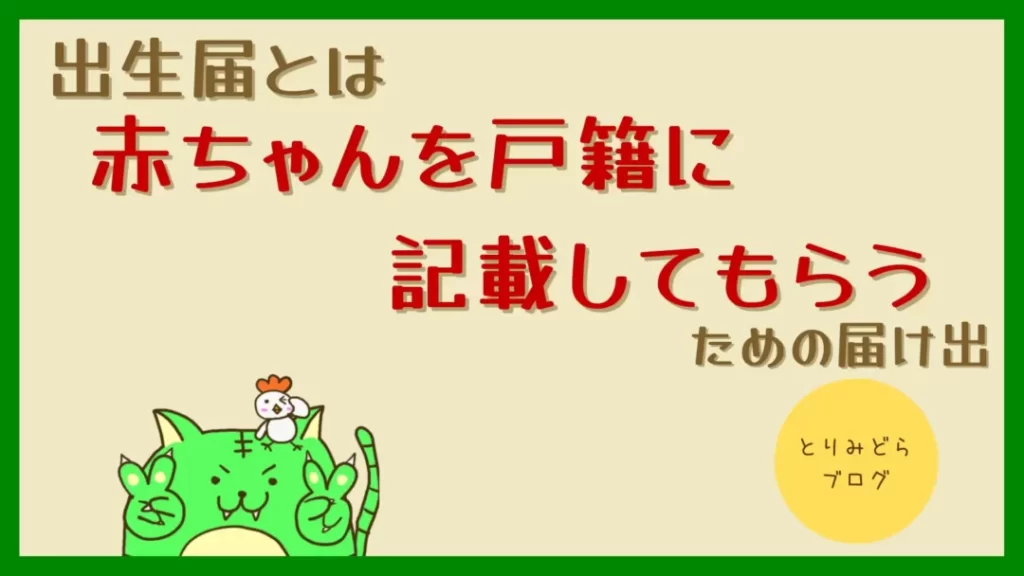
もうちょっとイメージしやすく言うと、赤ちゃんが生まれたことを国に知ってもらうための手続きというところでしょうか。
なので、全員必ず出します。
フォーマットは全国共通で横長A3サイズ、左側が「出生届」、右側が「出生証明書」になっています。
出生証明書は、出産した病院でお医者さんに書いてもらいます。
というかおそらく「出生証明書」を記入した状態の用紙をもらって、親があとから「出生届」部分を書くことになると思います。
 とりみどら
とりみどら病院によって違う可能性があるので確認しておこう!
- 届出人(窓口に行く人)
-
パパ or ママ
- 期限
-
出生日を含めて14日以内
- 必要なもの
-
- 出生届
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
役所には、「住民」や「戸籍」といったキーワードが含まれた名称の窓口がある部署があります。
そこに行って「出生届を提出したい」旨を伝えればOKです。
あとは「次はどこにいけばいいのか」を役所の方が案内してくれるはずなので、言われたとおりに動きましょう!
 とりみどら
とりみどら総合案内で聞くのが手っ取り早いかも!
児童手当
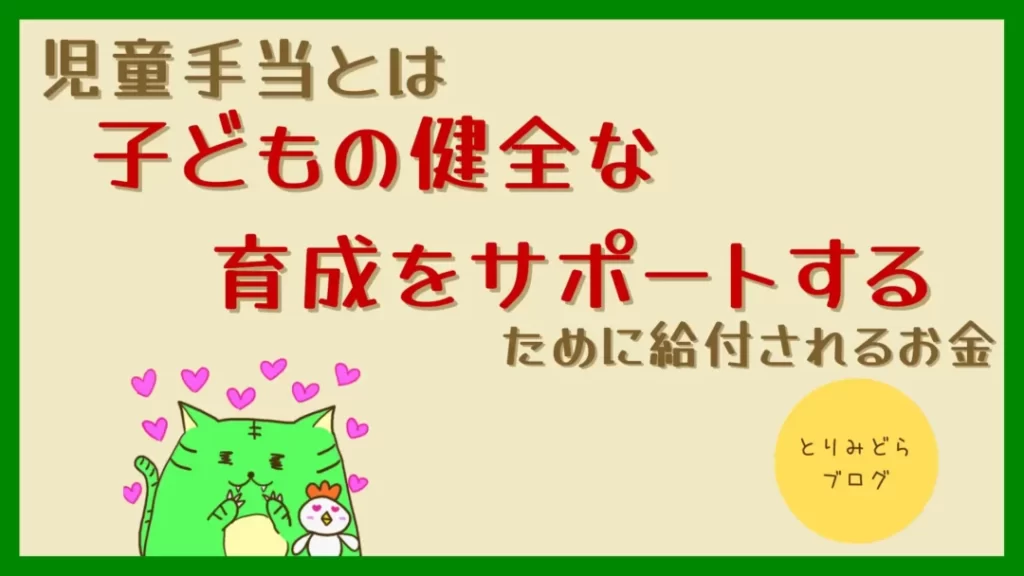
要は「子どもがいる家庭はお金がかかるから、ちょっとだけでも国がお金出すね」という制度があるわけです。
ありがたや~。
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、出産日が月末で、申請するのが月を跨いでしまった場合、原則に基づくと出産日の翌々月からの支給になってしまいます。
これを防ぐために、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、月を跨いだ申請でも出生の翌月分から支給されるルールになっています。
 とりみどら
とりみどら2週間以内に出せばゴチャゴチャ考えなくてOK!
- 申請者(窓口に行く人)
-
パパ (or ママ)(所得が高い方)
- 期限
-
出生日の翌日から15日以内
- 必要なもの
-
- 申請者・配偶者のマイナンバー確認書類及び申請者の本人確認書類
- 申請者の健康保険証のコピー
- 申請者の印鑑
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
- 手当の額
-
もらえる手当の額は、子どもの条件によって異なります。
- 3歳未満:15,000円
- 3歳~小学生(第一子、第二子):10,000円
- 3歳~小学生(第三子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
児童手当は、「子ども」「児童」「家庭」のようなキーワードが入った名称の部署が担当しているはずです。
おそらく誘導されてくるので迷う心配はあまりありませんが、困ったら上記のような名前の部署に行ってみましょう。
乳幼児医療費補助
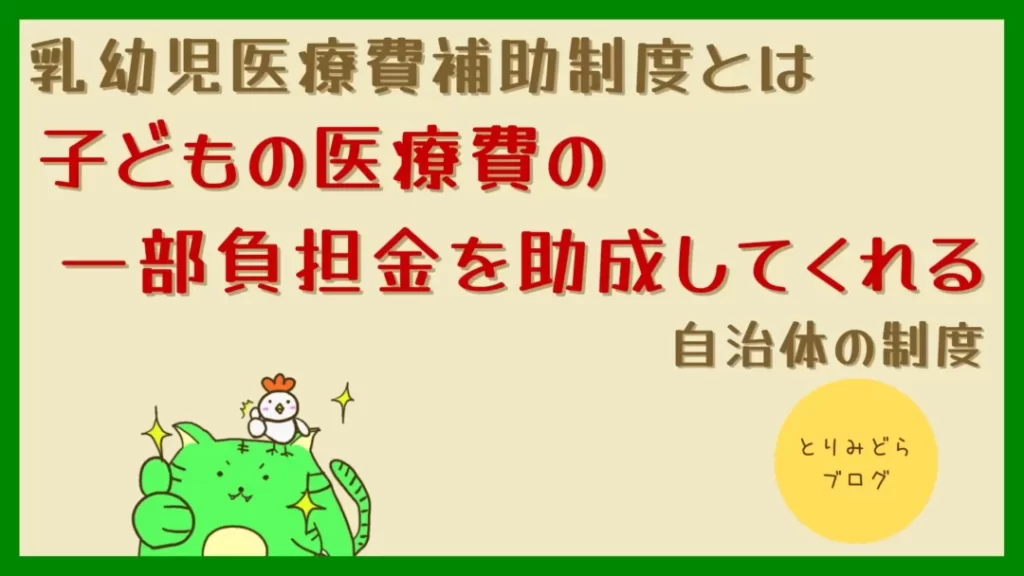
東京都ではマル乳と呼ばれているやつですね!
医療費は高額なので、後述する健康保険で国民全員で負担を分散して、窓口では1~3割負担になっているんですが、この制度は子ども分の窓口負担を自治体が肩代わりしてくれるんです。
つまり、子どもを病院に連れていくときは、基本的にお金を払わなくてよくなります!
なので、ちょっとでもおかしいかな?ってなったときに「でもお金かかるしな…もうちょっと様子見よう」とならずに連れていくことができて、子どもの健全な生育につながるわけです。
親としてはめちゃくちゃありがたいですね!
ものとしては、「医療証」が発行されます。
病院の窓口で健康保険証とこの医療証を一緒に出すことになるので、常に一緒に持っておきましょう。
医療証は母子健康手帳と同じくらいのサイズです。
中学生以下はほぼ確実に範囲内ですが、何歳まで適用されるかは自治体によって異なるようです。
 とりみどら
とりみどら自分の子どもが生まれるまで存在自体知らなかった!
- 申請者(窓口に行く人)
-
パパ (or ママ)(所得が高い方)
- 期限
-
出生日の翌日から15日以内
- 必要なもの
-
- 子どもの健康保険証
- 申請者の印鑑
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
乳幼児医療費補助も児童手当と同じで、 「子ども」「児童」「家庭」のようなキ ―ワードが入った名称の部署が担当しているはずです。
おそらく児童手当の前後にそのまま案内されると思うので、これも心配不要です。
出生届を出した時点ではまだ子どもの健康保険証が発行されていないはずなので、他のものを先に提出して、後日郵送で子どもの保険証のコピーを提出するケースが多いと思います。自治体によっては郵送で受け付けていない可能性もあるので、保険証の提出方法については確認しておきましょう。
その他
ここまでは代表的なものを挙げましたが、人によっては以下のようなものもあります。(以下は例)
該当するものがあるかどうか、事前にお住みの自治体HPで確認しておきましょう。
- 国民健康保険(扶養者が国民健康保険の場合)
- 出産育児一時金(出産した方が国民健康保険加入者の場合)
- 児童扶養手当(ひとり親家庭の場合等)
- 遺児手当(生計維持者が亡くなった場合)
- ひとり親家庭等医療費(ひとり親家庭の場合等)
- 未熟児養育医療給付(生まれた子どもが未熟児の場合) etc…
勤め先の手続き
健康保険
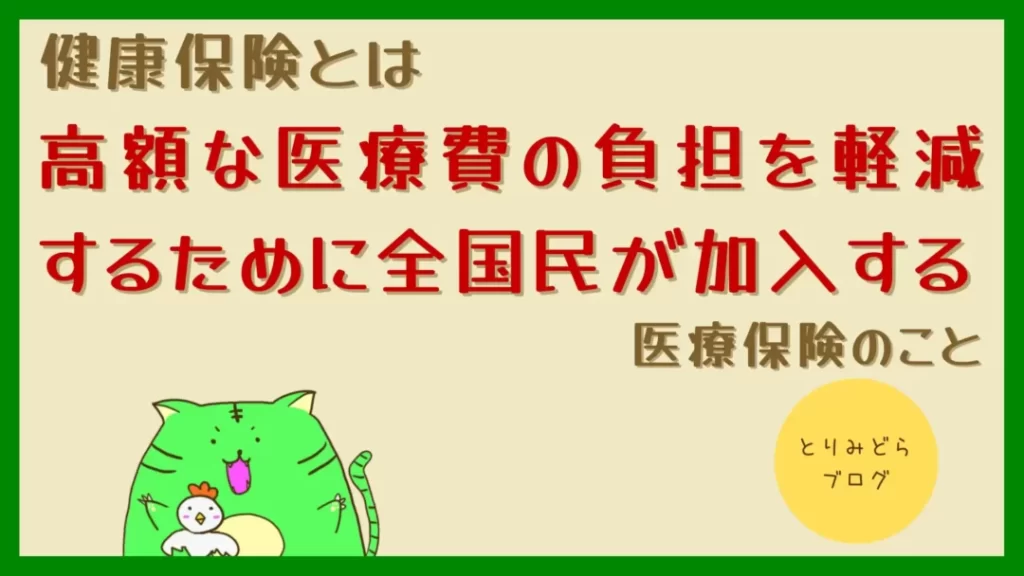
医療費は高額なので、「健康保険で国民全員で負担を分散して窓口で支払う額を軽減しよう!」という制度です。
この健康保険のおかげで、窓口で払う医療費は1~3割(割合は年齢によって異なる)で済んでいるわけですね。
皆保険制度を採用していないアメリカとかは医療費がめちゃくちゃ高くて、気軽に病院に行けないみたいです。
前述したとおり、健康保険+乳幼児医療費補助で10割カバーしてくれるので、子どもを病院に連れていくときは窓口でお金を出さなくて済みます!
健康保険にはいくつか種類があって、代表的なものだと以下の3つがあげられます。
- 健康保険
(会社勤めの場合) - 共済保険
(公務員の場合) - 国民健康保険
(個人事業主、自営業等の場合)
加入している健康保険がわからない場合は、保険証を見てみましょう。加入している健康保険の種類が書いてあります。
健康保険は保険なので、毎月保険料を払っています。
源泉徴収されているから勤め先に持っていかれている感覚になると思いますが、実は勤め先は代行しているだけです。
しかも事業主負担分というのも存在していて、支払うべき保険料の半額くらいは負担してくれているのです。
なので、
「毎月高い保険料持っていきやがってー!会社めー!」
ではなく、
「今月も負担してくれてありがとうございます!会社様♡」
と思っておきましょう(笑)
 とりみどら
とりみどらずっと加入してるのに、実は最近まで仕組み知らなかった!
- 申請者
-
パパ (or ママ)(所得が高い方)
- 期限
-
なるべく早く(健康保険証がないと乳幼児医療費補助の申請ができないため)
- 必要なもの
-
- 母子健康手帳の出生届済証明欄があるページのコピー
- マイナンバーが確認できるもの(住民票でOK)
子どもが生まれることは、あらかじめ会社の管理部門に伝えておき、
- どんな手続きが必要か
- 申請書類様式一式
- 必要な添付書類の種類と数
を確認しておきましょう。
上記のとおり、健康保険証は乳幼児医療費補助の申請に必要な上、お子さんを病院に連れていくときにも必要です。
健康保険の申請は最速で済ませましょう。
 とりみどら
とりみどら保険証、超大事!!
扶養控除等申告書
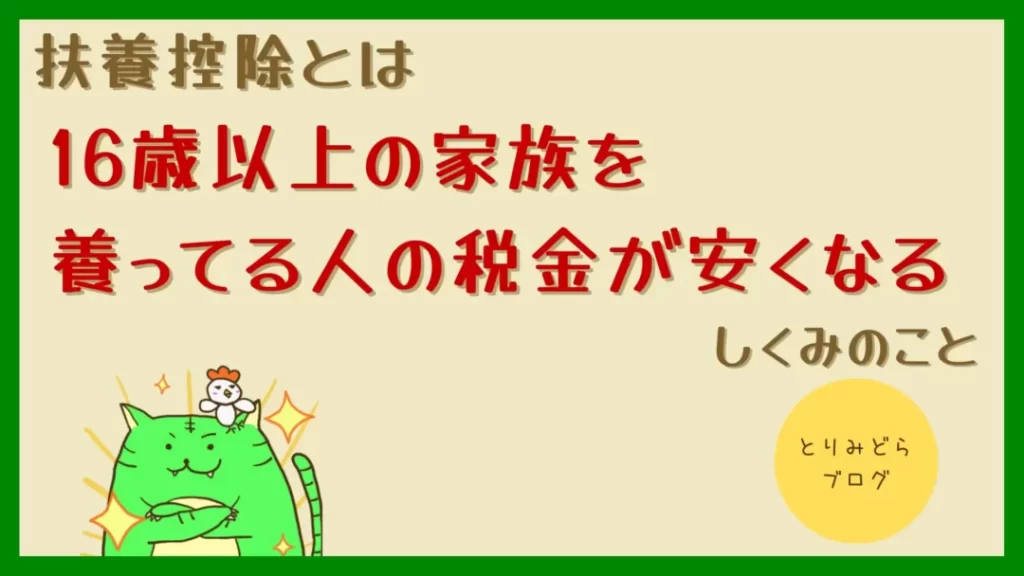
「自分が稼いだ分が自分の生活費だけじゃなくて家族の生活費にもなってるから、全部自分のものとして使える人より税金の負担を軽くしてあげようね」ってことです。
ありがたいですね!
 とりみどら
とりみどらありがたいしか言ってない気がする(笑)
扶養控除等異動申告書というものを職場に提出します。それが職場から税務署に行きます。
なんで16歳以上かというと、15歳以下は扶養控除の代わりが児童手当だからです。
中学校卒業と共に仕組みが切り替わる形になっているわけです。
なので、生まれたばかりの子どもがいても扶養控除が受けられるわけではありません。
「じゃあ申告する意味ないじゃん!」
と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
控除はないですが、「非課税限度額」は上がります。
この辺の話は趣旨から逸れるのでここまでにしておきますが、「申告する意味はあるし、申告して損をすることはない」と理解しておきましょう。
 とりみどら
とりみどら税金の話ってややこしいよね!
- 申請者
-
パパ (or ママ)(所得が高い方)
- 期限
-
なるべく早く
- 必要なもの
-
- 扶養控除等異動申告書
- マイナンバーが確認できるもの(住民票でOK)
- 住民票(世帯全員分)
- 配偶者の所得が確認できるもの(配偶者を扶養している場合は不要)
子どもが生まれることは、あらかじめ会社の管理部門に伝えておけば、扶養控除等異動申告書ももらえるはずです。
扶養控除等異動申告書にはマイナンバーを記入する必要があり、マイナンバーを証明する書類も必要です。
役所へ手続きしに行った際に、交付してもらっておきましょう。
育児休業
育児休業制度についてはイメージできると思うので、ここでは簡単に。
育児休業を取得する場合、主に2つの手続が必要です。
- 育児休業取得の申請手続
- 育児休業給付金の申請手続
これらは別々なので注意しましょう。
ただし、育児休業を取得する旨を管理部門に伝えれば案内してもらえるはずなので、あまり気にせず大丈夫です。
 とりみどら
とりみどらパパは絶対に育休とった方がいいよ!
その他
勤め先によってさまざまな制度があります。
事前に調べておくか、管理部門に問い合わせる等しておきましょう。
その他の手続き
出産関連費用の支払い(病院)
ママと赤ちゃんの退院日に出産費や入院費等の支払いを行います。
支払いの手続きの仕方や金額、支払うタイミング等は病院によって様々です。
退院時にバタバタしないよう、事前に確認して準備しておきましょう。
医療費控除(確定申告:税務署)
ざっくりいうと、「家庭内で年10万円以上医療費を支払った場合」、医療費控除が受けられます。
出産をした年は、家庭の医療費が多くなるので、医療費控除が受けられる可能性が高いです。
普段は確定申告してない方も税金が安くなる可能性があるので、きちんと確認して、必要があれば確定申告しましょう。
確定申告時期は、大体2月中旬~3月末です。
詳細は国税庁ホームページの確定申告のページで確認しておきましょう。
まとめ:手続はおやめに!

以上のとおり、子どもが生まれたらする手続きはたくさんあります。
正直、めんどくさいです。
めんどくさいですが、頑張りましょう!
 とりみどら
とりみどら頑張るぞー!!
手続は早めにやって悪いことはありません。
が、遅れると困ることが結構あります。
そして結構時間がかかります。
なので、早めに休みを取ってまとめて終わらせるのがオススメです。
不安でも大丈夫。それぞれの担当者がちゃんと教えてくれます。
役所では出生届を出せば、あとは流れのまま。会社では管理部門に問い合わせて、あとは言われたとおりにやる。
繰り返しになりますが、上記の内容は例ですので、必ず自分の自治体や勤め先に確認しましょう!
出産直後の母体は、大怪我しているようなものです。
そんな状態の中、初めての授乳をしたり、夜まとめて寝ることができなかったりと大変です。
手続きは大変ですが、ママの大変さに比べたらずっとラクです!
手続きは、パパとしての第一頑張りポイント!
ここで華麗にサッと手続きを終わらせて、ママの信頼を勝ち取りましょう!
- 手続きは早めにしよう!
- 役所は出生届さえ出せば、あとは言われたとおりでOK
- 詳細は必ず自分の自治体・勤め先で確認しよう!
- 手続きは新米パパの第一頑張りポイント!ママの信頼を勝ち取ろう!
今日はここまで。
おしまい!
1歳までの全イベント概要はこちら>>>【保存版】新米パパがおさえておくべき1歳までのイベントまとめ【新米パパ向け】
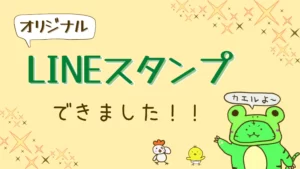
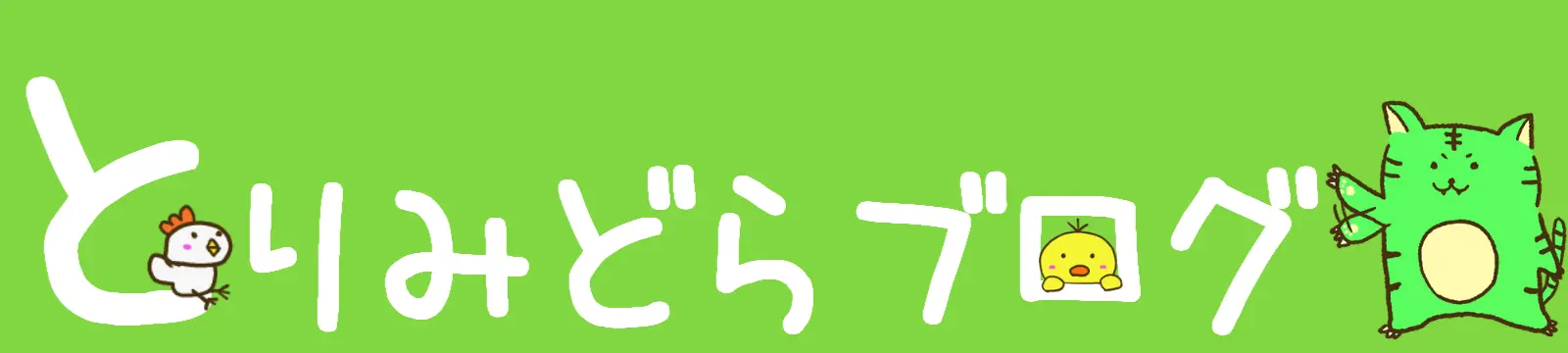

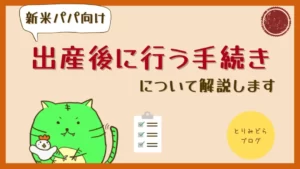
コメント